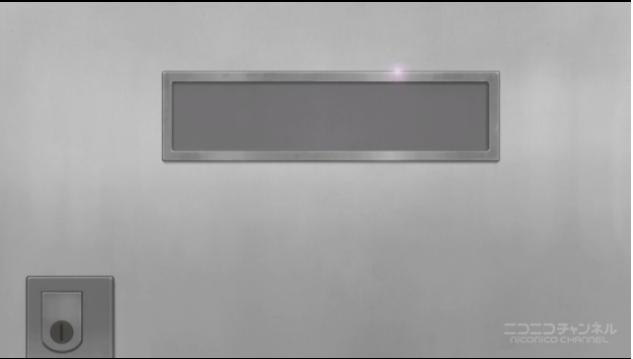第7話『大場なな』
この物語の全容が「少しだけ」明らかになった回。大場ななというキャラクターを通じて描かれる、その内容は予想外というよりはわりと予想の範疇に収まった感じでしょうか。舞台版を見ていると、ばななが一番闇が深い人物だったので何かあるだろうとは思っていました。ただここまで物語の鍵を握る人物だったのはちょっと意外ではありましたが。その得体の知れなさを紐解いていくと、一筋縄では行かないばななの背景がおぼろげに見えてきました。今回はその辺りをば、考えていこうかなと。
www.nicovideo.jp
今回も舞台版の筋も含むネタバレですので読み進める場合は以下をクリック(スマホなどで読まれている方はそのままお進みください)
【She is a Character】
まずは『キャラクター』の話をしようと思う。
今回の記事ではこの『登場人物』と『キャラクター』という区別を可能な限り、明確に分けたい。本記事においてのこの区別は分かり易くいえば、物語上に生きる人間と物語構造においての「記号」である。前者はもちろん、物語という「世界」において息づく人間である。我々となんら変わらない生活をする、架空の存在だが人間として作品世界に描かれる存在の事を指す。一方、後者は物語進行においての一種の機能である。描かれる物語があって、その物語を動かすために配置された歯車、あるいは展開上、不可欠な役割を与えられた部品といっても過言ではない。少なくとも後者においては、物語を彩る人間的な魅力が乏しいと言える。あくまで物語という機構を稼動させるための一部品でしかないからだ。
7話で描かれたばななは登場人物の内面が描かれる、というよりは物語に配置されたキャラクター記号としての役割説明の方が勝っていたように思える。それはつまりばななという個性についてはほとんど掘り下げられないまま、エピソードは描かれていた印象を筆者は持ったからだ。登場人物というよりキャラクターである。では、その記号であるばななはこの作品上においてどんな役割を持たされているのか。まずそこからは今回は切り込んでいきたいと思う。
7話のみならずここまで展開において、ばななが登場してきた時には彼女はスマホで写真ないし動画を撮っていることが多い。後述もするが、彼女にとっての「思い出」を収めるための行為である事には間違いない。しかし、少なくとも撮影者がばなな自身である以上、被写体または切り取られた風景には彼女は存在しない。当たり前のことではあるが、この点はかなり重要だ。アニメ版でも舞台版でもあれだけ「過去(思い出)」に固執していたばななであるはずなのに、その「思い出」を切り取る行為に自分を介入させていないのだから。
聖翔祭後の打ち上げ。7話の特色として、今まで以上にモブキャラたちがありとあらゆる場面で画面内に配置されているという点も踏まえておきたい。ピザについては8枚切りのデリバリーが2枚あるが、それが左:右(計)で7:8(15)→6:8(14)→4:7(11)→2:5(7)→0:2(2)という推移。何を意味しているのか、意図はあるのかどうかわからないが、あえて意図があるものとして掬ってみれば、8は「スタァライト」のメインキャスト人数なのでそれがどんどん減っていっているのを見ると、これから起こるレヴューオーディションの結果の暗示かもしれない。しかし、右が2切れ残るのに対して左がゼロというのが非常に気になる所。しかも2枚あるという辺りも今回提示された情報とはまた別軸かもしれない可能性もあるので予断は許せない。
ともあれ賑やかな打ち上げ会場を歩き回って、華恋たちを写真に収めるばなな。カメラレンズの先に見える光景の中には「自分」が入らないのは先ほども言った通り。もちろん写真はばななの視点から見えたものであるのは疑いようもないが、そこにレンズというフィルターが加わっている点に注目したい。自分の眼で見るよりカメラレンズによって切り取る事で、ばなな自らが見た印象すらも切り離しているのだ。思い出というよりはほとんど記録に近い。無意識の行為かもしれないがカメラを通じて主観が切り離されて、客観だけが残される。ばななはそうやって撮影していった写真に徹底的に自分を残さない。それは思い出の中に自分は必要ないと感じているからかもしれないが、真矢だけはばななの視線を意識して、自らも彼女へ視線を放つ。上に挙げた画像でも、真矢だけは強烈にばななの存在を意識していることに気付く。自分を意識しないばななとライバルと認めた他者を常に意識する真矢。この認識の差が今回のエピソードの軸のひとつでもあるだろう。
しかしその一方で俳優育成科、舞台創造科に限らず頼られていたことがクラスメートたちの口から語られる。それらが語られていく毎にばななの表情のアップショットがどんどんクローズしていく。同時に彼女という個性の存在感が徐々に強まっていくが分かるだろうか。他者からの承認を得て、ばななの自己は確立されていくが裏を返せば、彼女は自分自身を承認していないようにも思える。
バナナとバナナマフィン。文字通りばなな(バナナ)から作られたバナナマフィンは受け取った者と彼女とを結ぶ絆の証でもあり、彼女と世界を共有するものとも言える。そしてこの場合の「世界」というのは、彼女が撮影した写真の中の「思い出」とほぼ同義であるはずだ。彼女の思い出に組み込まれることで、共有した者たちは写真の中に「永遠」に記憶される。しかし管理者であるばななは本来、その「記憶」に存在することは許されない(無論例外はあるがそれは後述)。
その一方で、ばなな(この時点はまだ「なな」)はここで初めて「ばなな」という愛称を華恋から与えられる。先ほどの自己確立と合わせて、彼女の存在がさらに明確な形で承認された。それはつまり彼女に物語上の個性を授けているのが華恋であることに目を引かなければならない。翻れば、それまでのばななには彼女を色付ける個性がなかった、とも言える。
ななが「ばなな」に再生産されることで彼女は生まれ変わっているのだ。みんなに受け入れられて初めて、彼女は「ばなな」となれた事が嬉しいし、同時に第99回聖翔祭が「大場なな」という登場人物においてはかけがえのない「運命の舞台」になったことも想像には難くないことに思える。物語という「舞台」において、「大場なな」という「記号」が「個性」となって生まれた事実。それが作品によって、彼女に与えられた役割でもあるのだ。
だが、鎌首をもだけているのはこのミロのヴィーナスだ。これもばななを象徴する意匠のひとつであるが、しかしこのあまりにも有名な彫像は今現在、この姿かたちが完成された造形として認識されている。かつては両腕が存在していた、完成された造形であったことは間違いないが、今その姿を知る人間は一人として存在しない。「未完成」であるがゆえに高い芸術性を放つ彫刻として、その評価を不動のものにしているのは筆者が語らなくても、おそらく芸術に疎い人でもその美しさには頷くはずだろう。
これをばななに当てはめるのならば、失われた両腕というのはおそらく「可能性」の事を指している。彼女がレヴューオーディションを競い合う時に戦う武器として大太刀、小太刀の二刀流であることもその連想を裏付ける要因だろう。彼女の手には二つの可能性がある。それは演出や脚本などの舞台を創造する可能性、もう一つは舞台少女として、舞台を生み出す可能性。このどちらもがばななの中にはあるはずだが、同時にそれは最初から「失われて」もいる。つまりミロのヴィーナスの造形よろしく、「未完成」である事がその芸術性や完成度を高めているのであれば、ばななのそれも「未完成」であるからこそ「可能性」が担保されているのである。逆説的ではあるが、彼女は自身の個性を保つが為に、「失われた」可能性をも持つことが出来ているのだ。あるはずがないものがあって、手が届かないものに手が届いている。逆も然り。
慣れてきた当たり前の孤独
舞台が変えてくれたわ
変わりたくないこのまま
次には私まだ進めない……
時間よ止まれ 大人にならないで
〜舞台版劇中歌「私たちの居る理由」よりばななパート抜粋〜
この舞台版劇中歌でも分かるように、ばななは未完成のパラドックスを抱えたまま、「舞台」を作り上げることによって生まれた、自らの「個性」を失いたくないキャラクターなのだ。3話でクロディーヌが双葉との会話で「天才少女も大きくなれば、ただの人」と言わしめるように、可能性が「失われる」かまだわからない時期イコール、未成熟(未完成)の青春時代にばななは自身のキラめきを誤って見出してしまっている。7話後半の「まぶしいの……」という台詞も、他者から個性を承認されたばななが眺める、自分が介在しない「思い出」に眩さを覚えているからこそ、言える台詞だろう。少なくとも、レンズという自らの作った壁の向こう側から見える「世界」とは、ばななには届かない光であり、「永遠」のものなのだ。
しかし、その未完成のパラドックスを抱えているということは、ばななの個性も非常に不確定なものだと言うことの証でもある。その証拠に彼女は登場人物とキャラクターという二つの側面でずっと揺らいでいることに気付く。登場人物としては、聖翔祭の打ち上げで与えられた「頼れるみんなの『おかあさん』」という個性が彼女を物語上の「人物」として肉付けているが、その一方では物語上の「記号」であることから逃れられない「キャラクター」でもある。
では、「キャラクター」としてのばななとはどんなものであるか。先ほど「個性を失いたくない」キャラクターであると評したが、言い換えてしまえばいつでも「個性を引き剥がせる」キャラクターであるということ。ばななというキャラクターにおいては個性は記号的なテクスチャーに過ぎず、今のところは彼女の背景によって形成される核や芯のようなものではない。今まで描かれてきた舞台少女たちとばななが決定的に違う部分はここにある。
その描かれる描かれないかに関わらず、「登場人物」たちはその「人物像」が形成された過去ないし環境や背景によって、物語に立つはずだ。そういった「登場人物」を「人物」たらしめ、滲み出てくるなにかを「個性」と称することが出来るが、ばななにおいてはその「個性」があまりにも即席に貼り付けられているのだ。現段階ではばなながどういう動機で聖翔音楽学園を目指し、その学び舎で何を得て、何を成そうとしているのか、がまったく見えてこない。さらに言えば、彼女の「私がここに居る理由」が第99回聖翔祭以外には見つからないのである。彼女の個性が生まれた「思い出」しか彼女を肉付ける背景がない以上、この背景を取り払ってしまうと無個性な記号と化してしまう。それが彼女のキャラクター(記号)性なのだ。
これらを踏まえて、二年生に進級して新学期のスタートを切った以降を眺めていくと興味深い場面がいくつかある。
ここも今回の特徴的なシーン。新しい教室でばななのカメラから映し出された風景。ここでも今までになくクラスメートのモブキャラが映し出されている一方で、ばななはある変化にも気付く。一年次にいたクラスメートがいない。ここで目を引くのは、俳優育成科のクラスメートを彼女が全員把握している点だ。これは物語構造上の仕掛けだと思うが、ばななは描かれる物語の枠外に立ってる。
例えば、創作においては物語は主要人物をそれを取り巻く関係者たちのみで紡がれていく。学園ものならば主役がいて、ヒロインがいて、主役とヒロインのそれぞれの友人がいて、担任先生がいて、という風に学校を舞台にしてみても、比較的小規模な人間関係によって作品は形作られている。同時に、その物語からはみ出た(描かれないと言ってもいい)、物言わないクラスメートたちも確かにその場に存在している。彼らは何も語らないにしても、主人公たちのやりとりなど教室起こることを眺めているはずだ。作中の傍観者、あるいは観測者。物語には関わらないが確実に物語の中には存在しているキャラクター(記号)たち。ばななはそんな枠外の人々すらも把握しているわけである。
ばなな自体、個性が貼り付けられた記号(キャラクター)だと考えるならば、華恋たちの繰り広げる物語とその枠外を自由に越境することが出来る存在だということになる。彼女はカメラレンズを通じて、作り上げた「世界」全体を把握し、行き来する。
ここで学級委員長である純那がいなくなった成瀬・逢坂の両氏が退学したという事実をクラスに伝えるが、ここもばななが彼女たちがいない事に気付いた直後、彼女たちが退学したという情報が物語に組み込まれているので、ばななが気付かない限り、彼女たちの名が出て来る事はなかったのかもしれない。ここもばななのカメラが物語を機能させていて、カメラを下ろすと彼女は枠外から物語に戻ってくる。
物語に戻ってくると、メインキャストがフォーカスされて、「枠外の人物たち」が画面外から追いやられる。しかし、ばななにとっては見ている視界が全体である以上、物語外の脱落も他人事ではない。純那とともにロッカーの名札を外す場面もけっこう重要だ。視聴者には顔も分からない、彼女の同級生という記号そのものが物語から排除されてしまう。もちろん夢破れて、学園を去っていったクラスメートの事後処理をしなければいけない、純那とばななの辛さは別にあるわけだが、個性が貼り付けられた記号としてのばななは「世界」の欠落にも心を痛ませているという仕組みも透けて見えるか。純那は「前に進まない」と辛さを飲み込んでいるが、ばななにはそれが出来ない。「思い出」の一部分が損失しているからだ。彼女の捉える「世界」は「思い出」として永遠に記憶されるはずである、しかし失われてしまった。損失とは忘却である。「思い出」が忘れ去られてしまうのは、常に「孤独」を抱えているだろうばななにとっては、孤独よりも耐え難いものにも思われる。個性を失いたくないキャラクターであるばななだからこそなおさらにその思いは強いのではないだろうか。
そういった出来事を経て、第100回聖翔祭のオーディションが始まった。ここでもばななは変わらず、カメラ越しに見える「世界」を物語の枠外から眺めている。カメラのフレームに収められた映像も主要な登場人物たちといわゆるモブキャラクターたちが混在する絵面になっているのは、枠外の人間たちであるモブキャラ(記号)の性質を持つ彼女のゆえだろうか。他方、彼女はまた「登場人物」としての個性もあるので、最後の画面でモブキャラが消えて、登場人物たちだけが写る画面になるのも納得する。
この「キャラクター(記号)」と「登場人物」という二面性はばななの抱える不安定なゆらぎである、とここまで言葉を変えて繰り返し語ってきた。この不安定さこそ、大場ななという存在の物語における特質であり、問題点だからだ。しかし、彼女を物語の登場人物として強烈に意識している人物がいる。天堂真矢だ。
真矢は枠外に下がっているばななをわざわざ物語側に引き戻してまで、接触しようとする。純那も彼女たちの接触に気付くが、踏み入っては来ない。無論、彼女もばななを「登場人物」として意識していることは間違いない(もちろんこの二人以外もだが)。だが、個性まで含めてばななを意識しているのは真矢をおいて他にいないだろう。彼女の強烈な意識によって、未完成の美を象徴するミロのヴィーナスが曇り空という不穏さで包まれているも、ばななのゆらぎに対しての懸念があるからだろう。
二人きりで話す場所を探しに園内を歩く真矢とばなな。ここでもばななは枠外の人物、モブキャラクターを意識しており、手を振り返している。彼女自身がそういった枠外の人物たちと近い性質(記号性)を持っているからだろう。性質が似ているからこそ、彼女たちとも寄り添うことから逃げない。物語の内側も外側も見えてしまっているからこそ、物語世界を総体を捉え、自らもその一部であろうとする。個性が突出するのではなく、この作品世界で役割を持った一キャラクター(記号)として全うしようとする姿は、言い換えてみれば古川監督がメインスタッフとして携わった「ユリ熊嵐」における「透明な嵐」になることに他ならない。
先の作品では、個性を均質化させようとする「同調圧力」のメタファーとして扱われていた。しかし、本作は何よりも「舞台演劇」が題材であることはとにもかくにも物語の大きな軸である。スポットライトに当たる者がいれば、その陰で支える者もいる。夢を叶える者もいれば、夢破れる者もいる。それはつまり、自分を輝かせることができる者もいれば、そうでない者もいるということ。
同じような事を真矢がここで語っているが、枠外のキャラ、記号として存在する人々、つまり無記名性の強い人間たちの苦悩や絶望、怒りを記名性の高い彼女は理解することができない。所以、それは彼女が物語という舞台に立つ役者であるからだ。しかし、ここで積み重ねられていく枠外のキャラクターたちの佇まいにもばななは共感してしまっている。彼女にとって、この聖翔音楽学園という世界が「未完成にして永遠の舞台」であるからだ。「未完成」に「永遠」を見出してしまっている以上、その舞台に存在する全員を失いたくないし、守らなくてはいけない。大場ななという記号(キャラクター)が物語に与えられた個性(役割)はまさにここにあるのだ。ゆえに筆者は次に挙げる画像が、7話の最重要カットだと考える。
だが、「登場人物」として大場ななを見た場合はどうだろうか? 真矢が言うように舞台少女としての資質に恵まれていながらも、ばななは物語から「与えられた個性(役割)」しか演じないのはなぜか。その答えがこの名札の入っていないロッカー。誰も使っていない、このロッカーの中身は当然がらんどう、つまり何も入っていない。これをばななに置き換えてみれば、一目瞭然だろう。ここまで語ってきたように、彼女は「ばなな」という個性を貼り付けられた、物語構造上の記号である。そういった性質のキャラクター(記号)である以上、「大場なな」という物語の中に生きる人間として捉えた場合、その内面は何もないのだ。
彼女の内面が虚無である。というのは言い過ぎかもしれない。が、本項の冒頭でも語ったように、第99回聖翔祭を経て、物語上の一記号にすぎなかった彼女が「ばなな」という個性として再生産されたことが「大場なな」の錯誤であるならば、「舞台少女」としての彼女はまだ生まれていないということになる。
上に挙げた画像も顕著で、真矢の語りに重なって記号である「枠外の人々」は一斉に(ばななへと)振り向く一方で、「登場人物」である双葉と香子は振り向かない上に「何かを決めかねている」行為が暗喩として彼女に投げかけられている。記号(キャラクター)であることと「登場人物」であろうとすること。「舞台少女」で「登場人物」である真矢にとっては、その「未完成の永遠」に拘泥して、存在を確定させないばななに苛立ちを見せるのは、物語構造としても頷ける構図だといえるだろう。
もっと高みを目指したい 次のステップに上がりたい
仲間? いいえ 私たちはライバル
目指すはポジション・ゼロ センターこそが主役の場所
仲間? いいえ 私たちはライバル
〜舞台版劇中歌「ポジションゼロへ!」より抜粋〜
引用した舞台版劇中歌は端的に「舞台少女」であるということについて語っている歌詞だ。ばななのいう「みんな」とはこの歌詞で語られるような切磋琢磨するライバルではなく、彼女の存在を認めてくれる都合のいい存在であり、真の意味で「仲間」はないだろう。ばななは自分を受け入れてくれた「永遠の舞台」に耽溺しているに過ぎないのだ。
真矢との会話後、青と赤の入り混じる夕暮れのベンチに座るばなな。去年の聖翔祭の写真を眺めながら思いを馳せていると、純那と華恋、まひると居合わせる、4人で写真を振り替えながらも、ばななは画面の中央には入らない。「みんな」と作り上げた舞台が大切だからこそ、彼女は自分から中央に立つことは出来ない。そのカメラに収められた「思い出」(世界)を支配するのはばななだからだ。ここまで問題にしているのは、ばななの認識する「世界」(思い出)というきわめて狭い範囲で発生している事に過ぎない。その点では自己認識の問題でもあると思うが、物語上において彼女の存在そのものが未確定である以上、現時点では深く掘り下げる事は難しい。彼女の「登場人物」として背景がほとんど皆無だからだ。
しかし、同時に「ばなな」という愛称を与えた華恋が「舞台は生き物、同じ舞台はありえない、私の立つ舞台こそ私の舞台」だとここで解を示しているのも非常に示唆的だ。バナナチップスの袋の封を切る動作もばななの抱える状況と密接にリンクしているに違いないだろう。だがこの時点では、ばななが華恋の方を見ずに夕暮れ空を眺めるばかりで上の空だ。
大場ななはキャラクター(記号)である。しかし「登場人物」との間で揺れ動く、未分化な存在でもある。色の混ざり合った空を眺めながら、彼女は何を思うのか。そして、何を見出してしまったのか。次項ではそこを深く掘り下げていこう。
【She is a Ruler?】
ばななが記号と人物という二つの間で揺らぐ物語上の存在だと前項で示したが、その特性が物語に作用するのかをこの項では考えていきたい。彼女は自身のスマホカメラで撮影した「思い出」(世界)の支配者であるが、物語的にはどうであるのか。今回描かれた大転回もいろいろ交えて語っていこう。
前項最後に取り上げた場面の直後、学生寮に戻ってスマホを眺めるばなな。ここで注目したのは、昨年の聖翔祭でのメインキャストの集合写真。これが現状たった二枚しかない「思い出」にばなな自身の姿がある写真だ。公演終演直後のオフショットだろうが、やりきった笑顔が印象的だ。この写真の中にいるばななは「登場人物」らしい生き生きとした表情でもある。この集合写真から以降の画面が、ばななのスマホの画面フレームをそのまま、視聴者の見る画面としても適用しているのが興味深い。
ばななの見ている画面からキリンからの「着信」に切り替わる瞬間が上手く捉えられているし、同時に彼女の「世界」にキリンが介入してくる演出となっているのも面白い。今回の記事で説明してきた点に覆いかぶさるようにキリンの存在が舞い降りてくるのはある種の天啓なのだろうか。
ここも重要なカット。「思い出」に没入していたばなながキリンからの「着信」を受けて、「可愛い」と呟く場面。まるで悪魔に魅入られるかのように地下舞台、レヴューオーディションの場へと誘われていく。ほとんど何の疑問もなく不思議な着信を受け入れてしまえるのは、個性の貼り付けられた記号としてのばななが物語に「動かされている」感じが強く残る。
地下劇場で待っていたのは本物のキリンと舞台を照らすまばゆい黄色いスポットライト。まだオーディション開演前の舞台らしく、所々荒廃しており、機材なども錆付いている状態。キリンが言うには「『舞台少女』たちのキラめきを感じれば、照明機材、音響装置、舞台機構が勝手に動き出す」ということ。ちなみに舞台版ではキリンではなく椎名へきる演じる学年主任、走駝先生が語っている説明だ。
だが、この説明をばななにだけ語るというところにアニメ版の意地悪さが垣間見える。いや、そもそもアニメ版放映当初から舞台版で明かされた情報がかなりオミットされたまま、物語が進行していっている(もちろん舞台版は一公演の限りある尺で展開しなければいけない制約があるにしてもだ)ので、このように物語の折り返し地点を過ぎて、設定が明かされるのにも何らかの仕掛けがある、と勘繰りたくなってしまうのだ。
何が言いたいのかといえば、昔の台所のかまどにしても何をするにしても種火が必要であるということだ。キリンの語る、レヴューオーディションの「舞台機構」全体も再び動き出すためには着火燃料が間違いなく必要であるはずなのだ。
普通の喜び、女の子の楽しみ
すべてを焼き尽くし、はるかなキラめきを目指す
それが舞台少女
〜1話「舞台少女」より台詞引用〜
元々、みんなに承認されて「ばなな」に生まれ変わった少女である。ばななにとっての「永遠の舞台」である根源はそこにあるわけで、少なくともトップスタァの座を競い争うレヴューオーディションはなんら魅力のないもののはずだ。だが、キリンはばななに甘く囁く。
「あなたの望むどんな舞台に立てるとしても?」
前項でも語ったようにばななは「舞台によって作り上げられた、自らの個性を失いたくない」キャラクターである。過去に何があったかはわからないが、承認欲求が満たされなかった、無個性(だと思い込んでいる)少女にもし自分を受け入れてくれる場と人間が生まれたのならば、何度再現したとしても、その満たされなかった欲求を満たしたいと思うのは人間の常なのではないだろうか。このキリンの甘言が言葉となって、出た時点で物語上の記号の性質を引きずっているばななにとっては、最初から答えが出ていたようにすら感じられてしまう。誘導されるべくして彼女は舞台に操られ、
こうやって、おそらくキリンはばななを着火燃料に使って、舞台を「再生産」させた。彼女のキラめきが「舞台再生産」の燃料に使われた、またはキリンの甘言を受け入れた事によって、物語構造上の記号(キャラクター)であるばななには新たな個性が貼り付けられたともいえる。
それは真矢にすら勝ててしまえるほどの実力。いや、その実力は真矢が語っていたように最初から持っていたのかもしれない。だが、彼女がその力を発揮できた陰にはキリンと彼女のキラめきによって「再生産」された舞台があるからに他ならないだろう。ばななのキラめきが種火となって、ほかの舞台少女たちの舞台装置などが創造されているのならば、それはもはや彼女の盤上で戦っているようなものだ。舞台全体がばななのキラめきによって動いているならば、「舞台少女」という記号となって戦う彼女におそらく敵はいないだろう。
こうして難なくトップスタァの座に就いたばななであるが、お気づきだろうか。7話のBパートに始まるこのばななのレヴューオーディションの参加理由、並びにレヴューシーン、その後の舞台と彼女の関係を眺めていても、一度たりともばななにスポットライトが当たっていないことに。ばななとキリンと舞台は相互関係にあるが、彼女が記号的存在である以上、キリン(もしくは舞台)の化身となって力を発揮出来るが、これも同じく先ほど言ったように「登場人物」、つまり「人間」としての彼女の内面は虚無であるため、彼女自身をすり抜けて、舞台を照らす光にしかならないのだ。
ばななはオーディションを勝ち抜いてトップスタァとなった。望む「運命の舞台」は彼女を生んだ、あの第99回聖翔祭。しかし、レヴューオーディションの舞台と同じように、彼女の心の中に潜む「思い出の舞台」はすでに届かなくて、まぶしくなるほどに光は強くなっているのだ。しかし、それでもなおばななは望む。それが永遠に届かなくても、彼女にとって夢のような幸福の日々だったから。
かくしてばななは星のティアラを使い、美しくまぶしい過去を繰り返す事になる。同じ舞台など繰り返されない事はわかっているにもかかわらず、それでもなお。記号の彼女は自分の個性を見出してくれた「みんな」と舞台を作り上げるために、同じ一年を何度でも何度でも繰り返し、彼女の「思い出(世界)」を「再演」するのだ。
ばなながこれまでカメラで撮影してきた行為と何も変わらない。記録として収めた「世界」を自分という再生機器を通じて繰り返して浸っている。言ってしまえば、「思い出」のVR体験だ。しかし、記号である彼女によって、この機械的に再生される思い出は「本物」には程遠い。それどころか、幾度となく繰り返すたびにその確度は遠のいていく。ビデオテープが劣化するように、ばななの中にある「永遠の舞台」は遠のけば遠のくほど、さらにまぶしさを強めて届かなくなっていく。
こうして美しい「思い出」(過去)への執着と思いを強くしていくばなな。しかし、キリンによって引き起こされた彼女のキャラクター像には何か見覚えがあったのも事実なのだ。過去に固執し、永遠を強く願い捜し求めた、そのキャラクター性。それを持つキャラクターに思い至るまでにはさほど時間はかからなかった。
美しい思い出を持つものだけが
願うことを許されるんだ。
あの頃が永遠に続いたならば。
今もあの頃のままでいられたならばと。
〜「少女革命ウテナ」より御影草時の台詞〜
そう、本作の古川監督の師匠に当たる幾原邦彦監督の代表作「少女革命ウテナ」に登場する、御影草時そのひとである。思えば彼が登場する、黒薔薇編(14〜23話)は今回の7話と共通する箇所が多数存在するのだ。
ウテナの黒薔薇編はかつて「永遠についての研究」を行っていた黒薔薇会と呼ばれた、100人の男子生徒が生き埋めとなっていると言われる根室記念館を背景に、本編の物語の枠外にいる人々が「世界を革命する力」を得ようとするシリーズだ。御影草時はその首謀者として描かれていく。
彼もまた千唾馬宮(ちだ・まみや)という美しき過去の亡霊に囚われ、彼を薔薇の花嫁に仕立て上げる事で「永遠」を手に入れようとする人間でもある。物語の本筋に触れてしまうので、仔細には語らないが草時もまた物語上のカウンターとしての記号的な役割を果たしながら最後、人間としての自分を再確認すると、自らが望んでいた事が「虚無」であったことに気付かされる、という筋のものである。
そして草時が枠外の人々をデュエリスト(決闘者)に仕立て上げる要因に使ったのは人間の仄暗い感情と「思い出」だ。彼は人の弱さに漬け込んで、深層心理を抉り、「世界を革命する力」の為の資格を植えつける。いわばコンプレックスを「戦う理由」に増幅させて、利用したのだ。
…という辺りにウテナと本作、ひいては7話で描かれた事の共通性を見出すわけだが、これがどこまで意図されたことなのかは定かではないと付記しておく。内容的には意識せざるを得ない、黒薔薇編だが筆者が見るに「少女☆歌劇レヴュースタァライト」という作品のテーマを考えていった結果の先に、偶然同じテーマに行き着いた、という印象を強く持つ。御影草時と大場ななとでは違う点もやはりあるからだ。一番大きなところで言えば、草時はその最後に至るまでは自ら手を下さなかったが、ばななは自らの「永遠」を求めて、戦う選択をしているという点では明らかだろう。もちろん時代的な価値観の差もあるが、描写される問題の向き合い方には変遷を感じるところだ。
では、ここから幾原監督とシリーズ構成の榎戸洋司氏の両氏による、御影草時について発言を引用しつつコメントを加えていきたい。以下の引用部分は驚くほどに、7話におけるばななこと大場ななの役割や立ち位置を示している。引用元については、幾原監督は全て「少女革命ウテナ」DVD-BOXまたはBD-BOXに封入されたブックレットの各話解説より、榎戸氏の発言は全て「少女革命ウテナ脚本集(上)薔薇の花嫁」(98年刊、アニメージュ文庫、徳間書店)に記載されたものである。なお、引用末尾にページの記載があるのが榎戸発言、特に記載がないのが幾原監督の発言。また先に挙げている、御影草時のモノローグもDVD、またはBD-BOXのブックレットより引用している。
あるとき、テレビで見た少女が言った。
「世界は“選ばれる人”と“選ばれない人”の二種類しかいない」
ドキッとした。
「選ばれないことは、死ぬこと」
と少女は言った。
そこをやってみることにした。
黒薔薇編のこと。
これは黒薔薇編の発端となった幾原監督の発言。二元論で語られがちな現代社会における若者の極端な一例ではあるが、真理を突いているように思えるもの。いわゆる競争原理、勝ち組・負け組(これもだいぶ古い言葉になってしまった)の論理を語っているが、黒薔薇編の「本編の主人公vs枠外の人々」という構図を見出した発言ともいえる。この辺りの構図は7話におけるばななの特異性にも重ねる事が可能だ。彼女は「登場人物」と「枠外の人々(記号)」に揺れ動く存在とここまで語ったように、本作の題材である「舞台」では競争原理が勝るはずなのにも拘らず、その原理から外れた場所から、ばななは「永遠の舞台」に居続けようとする歪みがあるのも確認できるはずだ。
デュエリストって、なんか思い込みの激しかったり、片寄った人ばかりですね、という手紙を書いた君。
その通り。
才能は欠落であるという。
(中略)
けれど、環境から疎外されて人が人間となったように、周囲にとけこめない彼らであるからこそ、一般生徒と異なり、デュエリストとなりえたのだ。
(中略)
黒薔薇編は一般生徒が環境から疎外されて、デュエリストになるまでの過程を描いた物語だ。(それは“世界”と出会うまでの物語だ)
(P.257)
同じくシリーズ構成の榎戸洋司氏が黒薔薇編を表した言葉がこちら。才能は欠落である、というのは才能が突出していればしているほど、他方面においてはなにかしらの短所がある、ということを端的に示した言葉だろう。ウテナで言うところのデュエリスト(決闘者)とはレヴュースタァライトにおける「舞台少女」と置き換えることが可能だろう。ウテナの作品世界ではデュエリストである者たちとそうでない者たちの溝は大きく隔たっているからこそ、一般生徒がデュエリストとして目覚める過程が黒薔薇編で描かれた。しかし、「舞台少女」とは聖翔音楽学園の俳優育成科の生徒全体を指す言葉でもある。そういう意味ではばななもすでに「舞台少女」である。しかし、その「舞台少女」たちの中でも舞台に選ばれるものとと選ばれないものがいる。ウテナにおいての「世界」とはかなり漠然とした表現ではあるが、レヴュースタァライトの「舞台」は明確かつ限定的に存在している事でよりその競争原理はドラスティックに行われる。ばななはその競争原理に乗って争われる「舞台少女」にはなれていないのだ。一般生徒がデュエリストになる過程を「“世界”と出会うまでの物語」と表しているように、デュエリストであるための(“世界”と向き合う)目的が必要だ。しかし、「舞台少女」の目覚めをばななは「美しい思い出」に依存している以上、「“世界”と出会う」チャンスにすら背を向けている。また「舞台少女」であるための目的も、「個性を失いたくない」一心で「未完成にして永遠の舞台」を守ろうとしているのはここまでで語ってきたとおりだ。繰り返しになってしまうが「登場人物」・大場ななとして「舞台少女」である目的が(語られて)ないからこそ、“世界”と出会えていないし、真の意味ではまだ「舞台少女」ではないのだ。
全ては御影自身が、自分のために作った幻(イリュージョン)だった。
(中略)
時子は失われた“現実時間”の象徴だった。その時子が御影を迎えに来ると言う。ようやく御影が失われた時間の幻から開放されるときが来たのだ。
(中略)
その場所を否定する者は、逆に、その場所からも否定される。
システムとは否定した瞬間、それこそが自分の立っている足場であることに気づかされるものだ。
この発言も重要。御影をばななに置き換えてみれば、ウテナを見た事がない人でもなんとなく理解は出来るだろうと思う。時子というのは御影の想い人だが、これを本作の関係に置き換えると、ばななと純那の関係であると思われる。思えば、みんなが「ばなな」呼びしている中で、純那だけは変わらず「なな」と呼んでいる事からも分かるように、「ばなな」になる以前から彼女を単なる物語上の記号ではなく、隣人の「登場人物」として認識している。翻せば、「思い出(世界)」という幻覚に囚われたばななを不可逆な現実へと取り戻すのはおそらく純那の役割なのだろう。
ちょっと横道に逸れてしまったが、ここで目を引くのは「システムの否定」によって「立場が失われる」点。これも先ほど説明したように、相互関係にあるばななとキリンに舞台において、彼女がそれを否定してしまうのなら、それら全てが作り上げられた幻である事が暴かれてしまうという構図。と、同時に彼女の立場も失われる。その時、ばななは記号的役割から抜け出せるのか、というところが今後の注目点でもある。
以下に続く引用は一気に読んでいただきたい。どれも大場ななのキャラクター性を見事に言い表している文章のオンパレードで、その言葉の鋭さには打ち震えるほどである。置き換えて読む事を推奨したい。
鳳学園は、時空間の拘束すら受けない特殊な原理が支配しているようだ。
ではそれはなにか? この学園を支配する原理はなにか?
ポイントは弱さにある。
心象風景──夢とか記憶とか──と映像作品には共通するものが多くある。文法が似ているかもしれない。(その方程式を解けば、案外、現実も解体できるのでは、僕は考えている)
かつて“世界の果て”に選ばれたが、結局、あの永遠があるという城に到達できず、いまだにディオスの力を手に入れられない澱んだデュエリスト──それが御影草時である。
(P.255)
御影草時という名は、彼の本当の名前ではない。そして、その偽りの名前には、未練を残した想い人、時子の名が織り込まれている。
彼は、自分の弱さを自覚していない。
鳳学園という舞台は、弱さを軸にすべてが展開していく心象風景なのだ。
(P.256)
言ってしまえば──草時は最初から本当の人生を生きてはいなかった。
競争原理に支配された人生には、負けるときというのが必ずある。
大切なのは、負けたときに、それが負けであるということを認識することだ。
(中略)
草時は“閉じた人生”をおくっていた。自身が体験することに対してすら、常に傍観者であった。彼は優秀な評論家であったかもしれないが、いつしかプレイヤーの本分を忘れ、評論家以外のスタンスを見失っていた。森羅万象のすべてが、ガラス一枚隔てた“向こう側”のことになってしまっていた。
体験により自分が変わる、という前提を、彼はついに持てなかったのだ。
それは、なまじ才能があると陥りやすい、楽な生き方である。
楽な、しかし、結果的にはあらゆる豊かさを損なう、危険な生き方である。
(中略)
才能あふれる草時には、なにが足りなかったのか? 才能と“実力”は、本当は似て非なるものだと思う。才能とは、現実の可能性でしかない。だが実力は、現実そのもののことだ。
(P.258)
いかがだろうか。ここまで説明してきたように、ばななが「登場人物」と「枠外の人々(記号)」の間に揺れ動く存在で、なおかつその内面に抱えているものが虚無である事、さらには「思い出」に自らを反映させない事や、その「世界」を繰り返し追体験しようとしていることも、全ては彼女が「自らの弱さ」を自覚せずに体験によって、「自分を変える」という事を実感できなかった点に尽きると指摘されているような文言が立ち並んでいるのだ。才能豊かであった為に常に傍観者であろうとした事が、「思い出」へと溺れてしまう要因であるとも指摘している。特に「舞台」という競争原理のはっきりしている場所でそのシステムを否定した事により、自らの立場を失ってしまうという所は幾原・榎戸両氏ともに同調している部分であることもやはり踏まえてみると、ばななの持つ問題点の困難さが窺えるだろう。
潔く生きること。負けたとき、それが負けであると認めること。
世界に対して自分を開く方法が他にあるだろうか?
自分を開いて生きなければ、凍った時間に閉ざされたまま、一生が過ぎていく。
卵の殻を破らねば、雛鳥は生まれずに死んでいく。
(P.259)
では、どうすればいいのかの回答も上記引用に詰め込まれているわけだから、素直に脱帽だ。まさしく「卵の殻を破らねば、雛鳥は生まれずに死んでいく」という行為をばななはずっと繰り返し続けている。というより、彼女自身の執着によって、勝ち負けの判断もつけず、進歩や可能性すらも否定する「世界」は彼女だけにしか都合のいいものではないという事。それを打破するためにも、彼女は自らの抱える「思い出」をまず否定して、「過去は過去である」と認めなければ、先へとは進めない。
進化し続けるの そっと見守ってね
悔しさ後悔 その全てが ねぇきっと糧になる 明日の
〜「舞台少女心得」より歌詞抜粋〜
引用した楽曲にも言われているし、作中では華恋が言っているように舞台少女は「日々進化」しなければならないし、悔しさ後悔も未来への糧なのである。そしてこれこそが「舞台少女の条件」であるのだ。ばななはそこに気付かない限り、「舞台少女」として「登場人物」としてのスタートラインには立てないのではないだろうか。御影草時とばななが違うのは、先に待っている未来(可能性)の有無でもある。御影草時には追うべき未来はなかったが、大場ななには見据えるべき未来が待ち構えている。「枠外の人々」の境界を踏み越えて、「登場人物」として立つ時、虚無であった彼女の内面に何が詰め込まれるのか。興味は尽きない。
【The Scene Changes…】
さて、ここまでばななの抱える問題点をずっと語ってきたが、その変化の兆しもあったことを最後に語って締めたいと思う。以下の画像は、ついに舞台版でも描かれなかった戯曲「スタァライト」に登場する6人の女神たちの配役や展開が、7話の冒頭で語られた。


第1話で提示されたキャストオーディションのプリントを参照しつつ当てはめると、激昂の女神:純那、傲慢の女神:華恋、逃避の女神:香子、呪縛の女神:双葉、嫉妬の女神:まひる、絶望の女神:ばななとなる。ここまで描かれてきたエピソードから判断すると、納得の配役である事が確認できる。ばななが「絶望の女神」であるのは以下の画像で言い放つ劇中の台詞からも推察できる。
ああ また繰り返すのね
絶望の輪廻を
星明りの下で
〜7話より台詞抜粋〜
とまあ、ご丁寧にこの後、自らが辿る運命を示してもいるわけだから、言うに及ばずであるがやはり気になるのは「絶望」という所だろう。なにが絶望であるのかは、その後の展開や本記事かがここまで展開してきた内容をごらんいただければ、お分かりかと思う。つまりばななにとって「幸せな日々」を再演し続けることは同時に、彼女の「永遠の舞台」を極限までに理想化していく行為に間違いなく、その美化しすぎた理想に届かないからこそ再演を続けるという無間地獄を指して、「絶望の輪廻」なのだろう。
もちろんこれは、7話を通じて見ることができる視聴者(観客)だからこそ得られる視点であるのは否定しない。当事者であるばななはそのスタァライトの演技と、自分が陥ることになる境遇が重なることなど思いもしないだろうし、おそらく自覚もない。が、「運命の舞台」でばなな自身が演じる役柄でその台詞を吐露している事こそが、彼女の問題を解き明かす鍵でもあり「気付き」なのだろう。だからこそ、この公演をやりきったばななの表情はとても人間らしいのだ。おそらくこの直後の姿が収められたオフショット写真こそ、ばななの真の姿なのだと考えていいだろう。
しかし、そこへ辿り着くためには前項で引用した幾原・榎戸発言からもわかるように、「過程」が描かれなければならない。その為にはばななは自ら作り上げてしまった「永遠の輪廻」を打破する必要がある。が、彼女はまだそのことに無自覚である。
7話は全編を通じて、ミニマリズムに支配された描写が繰り返される。それはばななのループを表しているものでもあり、繰り返されることで発生する差異などもひっくるめて演出されているはずだ。この辺りは1話感想でも語った「ロシア構成主義」に起因する様式でもあるが、同時にばななが繰り返す「再演」もまた「同じ舞台」ではないことの証左にもなっている。
それは少しずつわずかにズレていく。何度も何度もそれを繰り返していくたびに、ある時点で積み重なったズレが大きな違いとなって表出して、すり替わっていく。その大きなズレこそがばななの「絶望の輪廻」を破壊する者であり、物語の特異点として、彼女の前に躍り出るのだ。
舞台少女がトップスタァになる瞬間
奇跡とキラめきの融合が起こす化学反応
永遠の輝き 一瞬の燃焼
誰にも予測できない運命の舞台
私は…それが見たいのです
〜7話キリンの台詞より抜粋〜
引用部分はキリンの目的なのだろう。ばななに「運命の舞台」を何度も繰り返させたことによって、生じた不確定要素。つまり「誰にも予測できない」状況を生み出すためにばななは「舞台」に利用されていたのではないか、という推測が立つし、同時にこの大きなイレギュラーが発生したことによって、キリンにとってのばなな(記号)の役割は終わってしまったようにも感じられる。
であるから、その不確定要素が現れるまでの一連のシークエンスはばななにとってミニマルに繰り返される光景であるが、同時に違和感とズレを感じているわけである。そのサインとして、1話の華恋の夢のシーンがあり、椅子から倒れ落ちる描写があったのではないだろうか。その証拠に、華恋が倒れた時にばなながはっとしているのも、なにかしら彼女の与り知らぬ出来事が発生しているからに違いない。
そしてそれは確信へと繋がる。ばななにとって予期せぬ大きなズレ。イレギュラーとして現れた神楽ひかりによって、物語という「舞台」は大きく動いていくことになる。
しかしばななは揺らがない。個性の貼り付けられた記号である以上、その与えられた役割を完璧に演じようとする。が、彼女がキリンと同調した記号であるならば、「同じ舞台じゃつまらないのかな」と「あの子(ひかり)も私の舞台にほしくなっちゃいました」はそのままキリンの考えをオウム返ししているようにも聞こえなくない。どちらにせよ機械的な動きをしている以上、「登場人物」としては動いていない。しかし、キリンの操り人形と化したばななの役割はひかりの登場で用済みとなっているとすれば、彼女は「運命の舞台」から追い出されているはずだ。なにせ記号は他にもいくらでもいるし、「舞台は生きている」のだから。
7話EDがインストであったのも、またキラめきを手で触れるのではなく、足で踏むのもおそらくはキリンとばななが呼応しているからなのだろうが、そこに「登場人物」として大場ななの意志はない。むしろキリンにとっては都合のいい記号でしかないし、キラめきはキリンにとっては「舞台」を動かす燃料でしかない。
だが、大場ななはそのキラめきに触れなくてはならないのだ。真の「舞台少女」としての大場ななが生まれる時、どんなキラめきが生まれるのか。それこそ誰にも予測ができない。ばななが自身に秘めた可能性を我が物として輝く姿を見せてくれることに期待を込めて、今回は締めくくりたいと思う。
※なお本感想はあくまで個人の印象によるものです、悪しからず。

- 出版社/メーカー: オーバーラップ
- 発売日: 2018/12/26
- メディア: Blu-ray
- この商品を含むブログ (4件) を見る

少女革命ウテナ脚本集 (上) (アニメージュ文庫 (N-90))
- 作者: 榎戸洋司
- 出版社/メーカー: 徳間書店
- 発売日: 1998/04
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 2回
- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 出版社/メーカー: キングレコード
- 発売日: 2008/09/26
- メディア: DVD
- 購入: 7人 クリック: 186回
- この商品を含むブログ (91件) を見る

少女革命ウテナ Blu-ray BOX 上巻【初回限定生産】
- 出版社/メーカー: キングレコード
- 発売日: 2013/01/23
- メディア: Blu-ray
- 購入: 12人 クリック: 207回
- この商品を含むブログ (35件) を見る