月一恒例の音楽鑑賞履歴。
今回から新体制での感想です。
といっても単純にはてなブログの下書き機能を利用して、商品リンクとTwitterに上げた感想を随時コピペするだけなのですがね。手間が若干増えましたけど、あんまり作業的には変わりがないのかなと。まだいろいろ試行錯誤してるので、細かな変更があるかとは思いますがよろしくお願いします。
今月は21枚。まあまあ聞けてますかね。微妙にヒップホップとエレポップ特集です。あと今年亡くなったジョン・ウェットンとアラン・ホールズワースの追悼感想があります。どっちも好きなミュージシャンだったので亡くなってしまったのはすごく残念。一時代を築いた人々がこれからどんどん亡くなっていくんだろうなと思うと、寂しくはなりますがそうやって時代は変わっていくんだなあと。
とまあ、そんなところで以下から感想です。

- アーティスト: SHAKKAZOMBIE,ILLISHIT TSUBOI,SUIKEN,DJ WATARAI,LORI FINE,SAIKOLEE TSUKAMOTO,DABO,H.IGUCHI,ブライアン・ウェルズ,T.KUBOTA,T.OSUMI
- 出版社/メーカー: カッティング・エッジ
- 発売日: 1999/07/23
- メディア: CD
- 購入: 1人 クリック: 4回
- この商品を含むブログ (24件) を見る
特にトラックメイキングの切れ味が全編にわたって、冴え渡っており合間合間に入るSkitやインストもとても聴き応えのあるものになっているのも目を見張るし、後半に行くと前作で押し出されていた沈痛なリリカルさも滲み出てきて、このグループならではの透き通るようなドープさが素晴らしい。
シークレットトラックになぜかスティーヴィー・ワンダーの「太陽のあたる場所」のパンクカバーが収録されているのはご愛嬌ながら、前作の持ち味を保ちつつ、グループの可能性を押し広げた作品だろうと思う。陰鬱な印象からわずかな光明に向かって、一歩前進し、重苦しさが少し軽くなった一枚。

- アーティスト: SHAKKAZOMBIE,MARTIN-KINDO,GAS BOYS,SRSAHNN,DABO,DELI,PH,Michico,SUIKEN,KASHI DA HANDSOME
- 出版社/メーカー: カッティング・エッジ
- 発売日: 2002/03/27
- メディア: CD
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (9件) を見る
そういう点では一番ヒップホップらしいとも言えるが、あのダークで透明感のあるメロウさがないので好き嫌いが分かれるところか。そういう点では装飾の多いサウンドテクスチャとも言える。クラブ向きのキャッチーなチューンもあるので、内容的にもパーティ感のある作品かもしれない。
ファンキーさに限らず、スパニッシュな音を取り入れていたりで、前作までの趣とはまた勝手が違うが悪くはない。この盤を最後にグループは活動休止となってしまうが、また彼らの曲を聴いてみたいと思わせる内容であり安定を求めず、前進する所に彼らの良さを感じる一枚か。いつか再始動して欲しい所だ

- アーティスト: Jamiroquai
- 出版社/メーカー: S2
- 発売日: 2001/09/03
- メディア: CD
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
リリース当時は、グループ自体がマンネリ期に入って、一時期の飛ぶ鳥を落とす勢いが減退しつつあったが、今改めて聞き直すと、彼らが15年前に提示していた音がここ何年かのトレンドになっているのと同時に、先見の明があったことに驚きを隠せないというべきか。当時は流石に今さらディスコかと思った
だが、ここで繰り広げられている音にはナイル・ロジャースばりのギターカッティングがあり、十数年後にダフトパンクが提示するディスコビートのブリリアントな輝きやソウルの甘い響きが詰まっているのだ。とはいえ、ビートがややもったりして軽やかさがないのに当時のニュアンスを感じざるを得ないか。
そういった抜けの悪さが、この盤が芳しくない評価を受ける一因に思えるし、実際、コンスタントに1~2年の感覚でリリースしていた、次作のインターバルが4年と空いてしまう事となる。失敗作とは言い難いが傷跡の大きい作品だろうか。内容は充実しているし、再評価されておかしくない出来かと。

- アーティスト: SOUL SCREAM,DABO,YO YO-C,UZI,MURO,BOO,HAB I SCREAM,B-YAS,E.G.G.MAN,DJ CELORY
- 出版社/メーカー: ポニーキャニオン
- 発売日: 2002/04/24
- メディア: CD
- クリック: 16回
- この商品を含むブログ (9件) を見る
前作が実直な形でソウルやファンクからの引用が多かったトラックも、今作ではバラエティに富んでおり、エレクトロやガラージュっぽいものやメロウなサウンドが入り込む辺り、ダンスフロア仕様になっている。そこへ乗っかってくるライムも日々の問題や環境問題など範囲が広くなり、より内容は濃くなった
そういう点では前作から正当進化したアルバムだと言えるが、前作のインパクトが大きい為か、今作の印象が割を食い、霞んでしまう形になっているのは惜しい所か。ポップなニュアンスも含んで、聞きやすくなっているし、楽しさではこちらに軍配が上がるかも。ただ彼らも本作で活動休止なのが残念だ。

- アーティスト: TVサントラ,雪野五月,沖野俊太郎,Hitomi,中川幸太郎,中川幸太郎 feat.鬼太鼓座
- 出版社/メーカー: ビクターエンタテインメント
- 発売日: 2005/09/22
- メディア: CD
- 購入: 4人 クリック: 14回
- この商品を含むブログ (50件) を見る
本作ではOPテーマ曲に和太鼓で有名な鬼太鼓座も参加したり、ED曲にはビーナス・ペーターの沖野俊太郎が歌っていたりもしていて、西部劇的な楽曲に限らず、遠い荒野の惑星で繰り広げられる物語をバラエティ豊かに色添えている。ストリングスとホーンの音に独特の雰囲気を感じる一枚だろう。

- アーティスト: TVサントラ,HITOMI,SHUNTARO OKINO,黒石ひとみ,ダミアン・ブルームヘッド,中川幸太郎,沖野俊太郎
- 出版社/メーカー: ビクターエンタテインメント
- 発売日: 2005/12/07
- メディア: CD
- 購入: 2人 クリック: 7回
- この商品を含むブログ (23件) を見る
とはいえ、後半の激化するバトルやそういった緊迫感のある展開に沿った楽曲ばかりなので聞いた感触としては重々しさや深刻さが伝わってくる為、あまり繰り返して聞けないか。簡単に言えば、エンニオ・モリコーニ調をさらにドラマティックにしている感じだろう。ドラマの最高潮を盛り上げる壮大な一枚。
・07年非売品OST。同名アニメ作品のDVD全巻購入特典で貰えたサントラアウトテイク集。公式発売された二枚のサントラから漏れた楽曲と最終話エンディングに流れたOPテーマの別バージョンが収録されている。収録時間は30分足らずなので、特典として送られるのも納得はする。
楽曲の方は二枚のサントラに収録されている楽曲のバリエーションが主。アレンジの違いでだいぶ雰囲気が違ってたりといった差異を楽しむことができる。曲調としてはシリアスなものや穏やかなものが多く、あまり派手さがないのと既存曲の変奏であることからサントラ収録からあぶれたのも頷けるか。
とはいえ、一番の目玉はシリーズEDで流れたOPのロングバージョン。鬼太鼓座の和太鼓による間奏が長く、物語の幕引きをうまく盛り立てている楽曲だろう。あと第1話のファーストシーンで流れてくる音楽もここに収録されている。今となっては入手困難だろうがファンなら粘って探す価値のある一枚かと
なお画像からも分かるように、このサントラはCDのジュエルケースではなく、DVDのトールケースなので、探す時は要注意。DVD全13巻の背表紙+このサントラの背表紙で一綴りの絵が完成するので、そういったコレクター面からも集めておきたい。

- アーティスト: ZAZEN BOYS,向井秀徳
- 出版社/メーカー: MATSURI STUDIO
- 発売日: 2006/01/18
- メディア: CD
- クリック: 37回
- この商品を含むブログ (299件) を見る
音の殺伐さとポストパンク感では本作が臨界点ギリギリの緊張感を出しており、曲によってはかなりアヴァンギャルドに突き抜けたものもあって、向井秀徳の読経的歌詞に乗せて、グルーヴを作り出そうとしているためにメロディらしいメロディがそこまでないというか非常にミニマルなバンドサウンドだ
工業製品のようなメタリックな質感が全編に渡って、彩られており、聞こえてくる印象は非常にヘヴィーなのがこの盤の特徴だ。なのでかなり重苦しさを伴い、繰り返して聞く頻度は少ない。全体的に質量が重いがサウンド的にはここまでが第一期。次作からは本作を起点に洗練の一途を辿る。密度は濃い一枚。

- アーティスト: Human League
- 出版社/メーカー: Blue Plate Caroline
- 発売日: 2002/11/21
- メディア: CD
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
無機質なシンセのビートとメロディがダークに鳴り響く一方で、ヴォーカルラインはR&Bなどの影響を感じるソウルフルな歌唱だったりする。そこの妙味が大ブレイクに繋がる要素であるが、本作ではまだ手探りな感触が拭えず、彼ら自身も自分たちの方向性をつかみかねている印象を受ける。
一方でクラウトロック、ひいてはプログレのような組曲形式の曲もあり、そこら辺のバランス感覚がかなり独特ではある。エレクトロミュージック(テクノ)とダンスミュージック(ファンク)の関係性を考える上で、この未分化なサウンドは歴史的にも重要だろうと思う。この盤で二つの要素が邂逅している。
全てシンセサイザーの演奏による、シーケンサーやループするビート、ミニマルで硬質なメロディがポップに響くのは、おそらく彼らが楽器を弾けず、演奏手段としてシンセサイザーを選択したことが大きく起因してるものと思われる。シンセの未知なる可能性を模索し、切り開いたのだと。
そこから掴み取ったアプローチがポップミュージックだったし、それが彼らのやりたい事だったように思う。この盤でもクラウトロック調の前衛的なものよりかはシーケンサーを最大限利用した、エレクトロファンク調のものの方がより魅力的に思えた。後の姿に比べるとかなり趣は違えど、可能性に満ちた一枚

- アーティスト: Human League
- 出版社/メーカー: Blue Plate Caroline
- 発売日: 2002/11/21
- メディア: CD
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
今作も全編に渡ってシンセサイザーのみの演奏で、この未来の楽器に対する彼らの試行錯誤が見え隠れはしているものの、ポップミュージックの方法論に則って、楽曲が構成されたことで、硬質で無機質かつダークに響く電子音からは前衛性が払拭され、バラエティに富んだメロディが聞こえてくる。
当然ながら、シンセの音にはまだ華やかさや色鮮やかさは感じられないが、英国独特のウェットな感触のメロディが工業製品のような機械音で奏でられることによって、先のインダストリアルにも通じるダークで耽美的なポップが展開されているのが興味深いし、その先駆者的な音が今聞くと面白くある。
後のエレポップ、あるいはテクノポップ、テクノの通る道をこのグループが一度通過していると思うと、歴史的でもあると思う。また前作もそうだが03年のリマスター盤にはボーナストラックが収録されており、本盤収録のものにはグループの分水嶺となった曲が収録されている。
それが16曲目の「I Don't Depend On You」だ。本作も前作も音楽性は高いが、売れ行きは芳しくなく、もっと商業的な音楽を出せ、とレコード会社から彼らが命令された結果、The Men名義で送り出された代物なのだが、これが災い転じて福となすを地で行く、起死回生となった
この曲はメンバーがシンセサイザーで作ったメロディを、あとでレコード会社がセッションミュージシャンを使い、生音のベースとドラムを重ねたものとなっており、当時のグループの信条に反した一曲なのだが、これが後に大ブレイクするグループの雛形となるから面白い。
生音のボトムラインが加わることで肉感的なグルーヴが生まれ、無機質だったサウンドに有機的な躍動感が出て、熱気を帯びた。メロディはシンセの電子音で、ビートが人間的な演奏というブレンド加減の絶妙さがとてもキャッチーな発明だった事が彼らの方向性を決定付けたのだ。
瓢箪から出た駒のような偶発的なものだったのだろうがこの鉱脈を推進する事となり、よりグループは商業的なポップミュージックへと傾倒していく。一方でシンセの可能性を突き詰めようとしたメンバーは脱退し、HEAVEN17を結成する事となる。NWという潮流を考える点では前作と合わせ重要な一作

- アーティスト: U2
- 出版社/メーカー: Island
- 発売日: 2007/12/10
- メディア: CD
- 購入: 1人 クリック: 3回
- この商品を含むブログ (7件) を見る
彼らの出身地であるアイルランドのシリアスかつ厳格な趣とアルバムのアートワークスに押し出されているモノトーンの色調がアルバムの荒涼さと寂寥な印象を与えており、そういったバンド特有の透明感と、本作のサウンドが合わさることで独特なサウンドスケープが表出している。宗教巡礼にも似た雰囲気。
彼らの持ち味の一つでもある、欧米社会に警鐘を鳴らすメッセージ性の高さも相俟って、ポストモダン的な張り詰めた緊張感が支配している為、なかなか気軽に聞ける作品ではないが、前述した趣がシンプルな魅力となってポップに響いた序盤3曲が彼らの代名詞になっているのも興味深い。格調高い名盤だろう

- アーティスト: Human League
- 出版社/メーカー: Virgin
- 発売日: 2012/06/04
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
80年に発表されたLM-1 Drum Machine(初代リンドラム)を活用し、生音の感触を残しながら、より人工感の強いポップソングを作り出していることに成功している。これによって前作までのシンセのダークな色合いの強いメロディ主体だった楽曲がよりビートポップらしくなった。
元々、ソウルフルな歌唱がグループの構成要素としてあった事と女性Voが加入したことによるボーカルの厚みも出たことも、キャッチーさも強化された一因だろう。当時の発言として、中心人物のフィル・オーキーが「エレクトリックABBA」を目指したとも言っていて、その意図も理解できる内容だろう。
アルバム構成的には全米でも大ヒットした10の「愛の残り火」をラストナンバーに持ってくることを意識した物となっていて、この曲の別格さがよく出ている。シンセのホワイトノイズとアナログだがデジタルなビートの半生な感触が蛍光灯のような明るさを放つ。時代を象徴する名盤の一つだ。なお12年に発売したデラックスエディションにて鑑賞。ボーナストラックも充実しており、ファンには嬉しい作りとなっている。

- アーティスト: ヒューマン・リーグ
- 出版社/メーカー: ユニバーサル ミュージック
- 発売日: 2015/11/04
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
それを踏まえてなお、この盤は全盛期の彼らを捉えた作品でもある。本作より曲によってはベースとドラムに生音を導入するようになり、よりソウルフルな質感が高まった。と同時に冷ややかな雰囲気も薄れ、体温を感じる温かみとシンセのめまぐるしい進化による音色の多彩さが強まって、華やかになった
そういう点ではこの盤収録のリミックスも含めて、充実した作品なのだが1の「Hard Times」の低音がホール&オーツの「I Can't Go for That (No Can Do)」だったり、他アーティストの楽曲を想起させるメロディラインが見受けられたりする。
もっとあからさまなのは3の「You Remind Me Of Gold」でサビが完全にクラフトワークの「The Robots」まんま。大ヒット作後でツアーなどに忙殺されていただろうとはいえ、練り込みが粗製な部分も否めない。が、楽曲として質は高いのでこれはこれで許容範囲か。
ブレイク後の勢いそのままに絶頂期の彼らの姿が窺える一枚として、EPながらかなり満足感のある一作だし、リイシューによって増補された所もあいまってアルバム一枚分のボリュームを楽しめることが出来るのがありがたいところ。80年代初頭の華やかなNWサウンドが好きなら聞いて損はない一枚だ。

Burning Bridges ~ Special Edition
- アーティスト: Naked Eyes
- 出版社/メーカー: CHERRY POP
- 発売日: 2012/11/20
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
70年代末〜80年代初めの硬質な音に比べると、本作のシンセの音は非常に柔らかい印象を持つ。トニー・マンスフィールドの淡い色彩感覚も影響が強く、水がパシャパシャと弾けるような瑞々しさがあるのが最大の特徴で、そういった雰囲気が英国ならではの湿り気を帯びたメロディと重なっている。
生音というか、ベースやギター、ドラムなどの人力演奏もフェアライトの旋律に絡んでいるのもあり、エレポップながら透明感やナチュラルな響きを演出しているのが面白く、サウンド的にはNew Musikの延長線上にある点でも非常に興味深い作品である。かといってオーバープロデュースになってない
60sポップスをエレポップに落とし込んだようなエヴァーグリーンな響きを作り出しているのは他ならぬグループの二人であり、トニー・マンスフィールドはプロデューサーとして自分の個性を彼らに寄り添わせているし、波長が合ったという事なのだろう。意外とNY的な洒脱感も匂わす、80sの良盤だ。

- アーティスト: Tango In The Attic
- 出版社/メーカー: Thomason sounds
- 発売日: 2012/04/29
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
ストロボライトが絶えず点滅して、視界を遮り、ホワイトアウトしていくサウンドの鮮烈さやドリーミーなメロディが突き抜けていて、そのイメージの奔流に押し流れてしまいそうになってしまう。そうやって焼きついた残像が煌びやかな光の中に溶け込んでいくさまが美しくもある。個性を一段と強めた一枚。

- メディア:
- この商品を含むブログを見る
ミディアム〜スローナンバーでも甘くならない、武骨かつ辛口な演奏もなかなか味わい深く、スワンプロックさながらの泥臭さと現代っぽさも兼ね備える、ギターフレーズの芳醇な響きが冴え渡る。モダンブルースとしても、ブルースロックとして聞いても十二分に楽しめる良作。骨太なギターを味わえます。
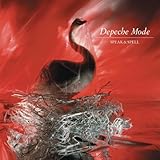
- アーティスト: Depeche Mode
- 出版社/メーカー: Mute
- 発売日: 2013/08/01
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
やはり80年代に入るとシンセサイザーで奏でられる音数が増えてその分だけ、多彩なサウンドになっているのが特徴で、本作もその恩恵を受けている作品といえるだろう。シンセサイザーだけで演奏が構成できる時代に突入した事が伺える近未来的なサウンドがやはり楽しいか。
とはいえ、ポップなサウンドではあるが同時期に存在していた他のエレポップユニットに比べても、彼らはやたらと筋肉質でマッシヴな印象を感じるか。他のグループが耽美的な趣を持つ一方で、硬質でしなやかなバネを持った音といえばいいだろうか。低音がずっしりと響く感じがそういうイメージを強める。
メロディもブラックミュージック起因のものというより、クラシックや賛美歌と言った厳格さや重厚さがまず先に立って、よりマナーというか形式に従ったものに沿って、奏でられている。神聖なもの、と言うと流石に言い過ぎだと思うが宗教的な響きが感じられた。もちろんソウル的なフレーバーもある。
本作はヴィンス・ニールの一人舞台であり、彼の個性が前面に出ているものばかりだが、ヒットした曲にはやはりポップソングマナーともいうべきR&B調が混ざっているのが興味深いか。既に完成された音がゆえに、彼は一作のみで脱退、残されたメンバーは活動を続ける事となる。迷いなく傑作の一枚だろう

- アーティスト: Depeche Mode
- 出版社/メーカー: Mute
- 発売日: 2013/08/01
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
中心人物だったヴィンス・ニールの脱退を経て、マーティン・ゴアがサウンドの中核となった事がこの大きな変化をもたらしているが、前作では感じられなかったセンシティヴな繊細さと情感豊かな緊張感が影の濃さを伴い、厳格に響くのが一線を画す。他のエレポップ勢と比べても芸術性の高さを感じる。
ポップなテクスチャーから剥き出しになったアーティスティックな一面がグループの作風として認知されることによって、以後30数年に渡る息の長い活動を支える原動力になっているのは間違いないだろう。意外に、低音とリズムの響きに拘りのある作品。エレクトロの音楽性を一段階上に持ち上げた重要作だ

- アーティスト: Tony Williams
- 出版社/メーカー: Sbme Special Mkts.
- 発売日: 2008/02/01
- メディア: CD
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
本作に収録されているアルバム二作の注目どころはなんと言っても、ギターのアラン・ホールズワースの参加だろう。渡り鳥ミュージシャンである彼が二作続けて全面参加というのはかなり珍しいといえる。しかもアメリカの音楽シーンに呼ばれての参加なのも、割と異色さが際立つ。
内容は同時多発的に世界で勃興しつつあった、ジャズロック/クロスオーバー(後にフュージョン)的なサウンドで、リーダーのトニーをはじめとした、密度の濃い演奏が繰り広げられている。時代的な音といえばそれまでだが、当時の熱気は確実に伝わってくる、鋭い切れ味には目を見張るか。
ホールズワースの活躍度から言えば、断然「Believe It」に軍配を上げる。楽曲を2曲ほど提供しているのもあって、このメンバーで作り出されるケミストリーが味わえるし、アメリカンミュージック起因のカラッとした味わいにあの独特で湿度の高い高速フレーズが混ざり合う、不思議さが妙味だ。
対して「Million Dollar Legs」の方は、「Believe It」に感じられるスペーシーな感覚が薄れ、よりファンキーな路線へとシフトしているために、ホールズワースの存在に場違いな印象を受けるのが惜しいか。実際プレイの方も、お仕事として割り切っている雰囲気を感じる。
とはいえ、ラストナンバー(本作の13)でそれまでの鬱憤を晴らすようなソロを繰り出していて、面目躍如な趣も。トニーのドラムについては、後進への影響が多大すぎて、当時は先進的だった演奏もあまり目新しさがないように感じられてしまうのは後追いの弊害だろう。一粒で二度味わうには格好の一枚。

- アーティスト: King Crimson
- 出版社/メーカー: Virgin
- 発売日: 2001/01/29
- メディア: CD
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
Yesから引き抜いてきた、ビル・ブルーフォードのドラムとパーカッションのジェイミー・ミューアの変拍子が強調され、西洋の音楽形式から離れて、よりフリーフォームな音楽に移行した感もあるのが当時としては斬新だったし、今聞いてもその切れ味については衰えを知らない鋭さがある。
後にポリリズムを積極的に取り入れていくことになるが、特にリズムへの追求(と即興演奏)に音楽性の活路を見出したことと前作までの叙情性がうまくブレンドされたことでバンドの可能性が大きく広がったのは言うまでもない。全編にシリアスな緊張感がメタリックに響き、宗教的でもある。
エスニックな響きも奏でるデヴィット・クロスのヴァイオリン、さらにはバンドの叙情性を一手に引き受ける、ジョン・ウェットンのメランコリックな歌、どれ一つとして欠けることが許されない、クリムゾンが一つの完成形を見た作品でもある。代表作にして名盤。が、それはほんの一瞬の煌きでもあった。

- アーティスト: フリー・デザイン
- 出版社/メーカー: SOLID
- 発売日: 2015/12/16
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
バカラックなどのオールドタイムなアメリカンポップスを下敷きに、時にさわやかに、時にドリーミーに繰り広げられているが、バンド名と同様、自由自在に複雑怪奇なメロディと演奏が織り交ぜられるのには舌を巻く。一歩間違えば、白昼夢的なサイケ/プログレサウンドなのだが、ポップスの縛りが功を奏す
ブライアン・ウィルソンが提唱した、ポケット・シンフォニーというでも言うべき音を事も無げに成立させているメンバーの手腕、そのポップネスには感嘆せざるを得ない。アルバム全体もぴんと張り詰めた緊張感の下、さっと溶ける砂糖菓子のように儚げさを感じさせる。最高傑作という呼び声も高い一枚だ。
